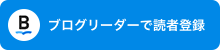弁護士の満村です!
今回は、タイトルの裁判例を紹介します(福岡地判令和04年03月18日 事件番号:平成31年(ワ)第1170号)。
有名な東名高速道路あおり運転事件( ニュース記事 )の被告人と同姓であったために、とある掲示板上で被告人の父親だと名指しされたAさんが投稿者を訴えた事件です。
実際はAさんは父親ではありませんでした。
こういう特定班的なネットユーザーってよく見ますよね。
有名事件の真相を推測も交えて論じることでPVを稼ごうとするある種のトレンドブログのようなものもよく見かけます。
「犯人〇〇の家族は!?恋人はいるの??」みたいなやつです。
まあ、そういうお転婆なネットユーザーさんがちゃっかり訴えられたということですね。
今回注目する投稿は以下のものです。
訴えられた投稿:「これ? 違うかな。」
です。
え??
という感じですが、
この投稿は、 「(被告人の)親って〇〇区で建設会社社長をしてるってマジ? 息子逮捕で会社を守るために社員からアルバイトに降格したの?」という内容の投稿に対する返信の形式で、B社(=Aさんの会社)の所在地や電話番号等が表示されるサイトへのハイパーリンクが設定されたURLも付してなされたものでした。
確かにこうなると前後の文脈からして、思いっきり特定の会社とその社長の社会的評価を低下させそうです。
でも、これって、「これ?」「違うかな」と質問形式なので、事実を断定していなくないですか?
当然、被告からはそのような反論が出ました。
しかし、裁判所は、
「「これ? 違うかな」として断定した表現を避けてはいるものの、本件返信元記述の問いかけに答えるもので、本件返信元記述の記載内容の真実性に対して何ら疑問を呈することなく、かつ、本件投稿1を投稿した経緯の説明を付すことなく、本件返信元記述の内容を前提に、これに沿ったB社の情報を摘示したものであるから、本件返信元記述の信用性を高め、かつ、会社の名称や所在地を明らかにするハイパーリンクが設定されたURLを掲記し、情報の精度を上げるもので、本件投稿1の読者に対し、本件男性が本件会社に勤務し、B社の代表者が本件男性の親であるとの印象を与えるというべきである(一部単語の修正あり)」と判断しました。
投稿の違法性を判断するには、その投稿そのものだけを見ていればいいわけではないということがよく分かる事例ですね。
以上のように、この投稿について名誉棄損が認められました。
で、この慰謝料は、というと、 20万円+弁護士費用2万円でした。
安いですね~ここまでがっつりした名誉棄損なのに。
でも、これにはちょっと理由がありました。
・Aさんが報道機関に働きかけ、本件の虚偽情報が事実と異なる旨が繰り返し報道されるなどした
・Aは、B社とともに、本件虚偽情報に係る名誉毀損に関して、被告ら以外の者から合計約230万円の支払を受ていた
・被告らが、Aの告訴等を受けて本件各記述について、B社に対する名誉毀損罪が成立するとして、それぞれ罰金30万円の判決を受けた
とのことです。
報道があって、嘘がある程度修正されていると判断されれば慰謝料下がるんだ!
他人の慰謝料の支払でも関係あるんだ!
投稿者が刑事罰を受けていれば慰謝料が下がるんだ!
とか、少し気付きがありますよね。
はい、そんな感じでした。
ネット上では、大して調べもせず、「〇〇さんは××らしいよ」「〇〇さんの言ってたことは嘘で××が正しいらしいよ」みたいな推測の域を出ない発言が多く見られ、今日も人々の心を惑わしています。
我々法律家からすると、そのような「根拠なんて要らない」と言わんばかりの態度には驚くばかりです。
「根拠」の無いことへの危機意識をしっかり持ってこのネット社会を生きていきたいですね。
では!
法律相談は、mitsumura@vflaw.netまで。

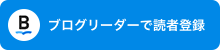
今回は、タイトルの裁判例を紹介します(福岡地判令和04年03月18日 事件番号:平成31年(ワ)第1170号)。
有名な東名高速道路あおり運転事件( ニュース記事 )の被告人と同姓であったために、とある掲示板上で被告人の父親だと名指しされたAさんが投稿者を訴えた事件です。
実際はAさんは父親ではありませんでした。
こういう特定班的なネットユーザーってよく見ますよね。
有名事件の真相を推測も交えて論じることでPVを稼ごうとするある種のトレンドブログのようなものもよく見かけます。
「犯人〇〇の家族は!?恋人はいるの??」みたいなやつです。
まあ、そういうお転婆なネットユーザーさんがちゃっかり訴えられたということですね。
今回注目する投稿は以下のものです。
訴えられた投稿:「これ? 違うかな。」
です。
え??
という感じですが、
この投稿は、 「(被告人の)親って〇〇区で建設会社社長をしてるってマジ? 息子逮捕で会社を守るために社員からアルバイトに降格したの?」という内容の投稿に対する返信の形式で、B社(=Aさんの会社)の所在地や電話番号等が表示されるサイトへのハイパーリンクが設定されたURLも付してなされたものでした。
確かにこうなると前後の文脈からして、思いっきり特定の会社とその社長の社会的評価を低下させそうです。
でも、これって、「これ?」「違うかな」と質問形式なので、事実を断定していなくないですか?
当然、被告からはそのような反論が出ました。
しかし、裁判所は、
「「これ? 違うかな」として断定した表現を避けてはいるものの、本件返信元記述の問いかけに答えるもので、本件返信元記述の記載内容の真実性に対して何ら疑問を呈することなく、かつ、本件投稿1を投稿した経緯の説明を付すことなく、本件返信元記述の内容を前提に、これに沿ったB社の情報を摘示したものであるから、本件返信元記述の信用性を高め、かつ、会社の名称や所在地を明らかにするハイパーリンクが設定されたURLを掲記し、情報の精度を上げるもので、本件投稿1の読者に対し、本件男性が本件会社に勤務し、B社の代表者が本件男性の親であるとの印象を与えるというべきである(一部単語の修正あり)」と判断しました。
投稿の違法性を判断するには、その投稿そのものだけを見ていればいいわけではないということがよく分かる事例ですね。
以上のように、この投稿について名誉棄損が認められました。
で、この慰謝料は、というと、 20万円+弁護士費用2万円でした。
安いですね~ここまでがっつりした名誉棄損なのに。
でも、これにはちょっと理由がありました。
・Aさんが報道機関に働きかけ、本件の虚偽情報が事実と異なる旨が繰り返し報道されるなどした
・Aは、B社とともに、本件虚偽情報に係る名誉毀損に関して、被告ら以外の者から合計約230万円の支払を受ていた
・被告らが、Aの告訴等を受けて本件各記述について、B社に対する名誉毀損罪が成立するとして、それぞれ罰金30万円の判決を受けた
とのことです。
報道があって、嘘がある程度修正されていると判断されれば慰謝料下がるんだ!
他人の慰謝料の支払でも関係あるんだ!
投稿者が刑事罰を受けていれば慰謝料が下がるんだ!
とか、少し気付きがありますよね。
はい、そんな感じでした。
ネット上では、大して調べもせず、「〇〇さんは××らしいよ」「〇〇さんの言ってたことは嘘で××が正しいらしいよ」みたいな推測の域を出ない発言が多く見られ、今日も人々の心を惑わしています。
我々法律家からすると、そのような「根拠なんて要らない」と言わんばかりの態度には驚くばかりです。
「根拠」の無いことへの危機意識をしっかり持ってこのネット社会を生きていきたいですね。
では!
法律相談は、mitsumura@vflaw.netまで。